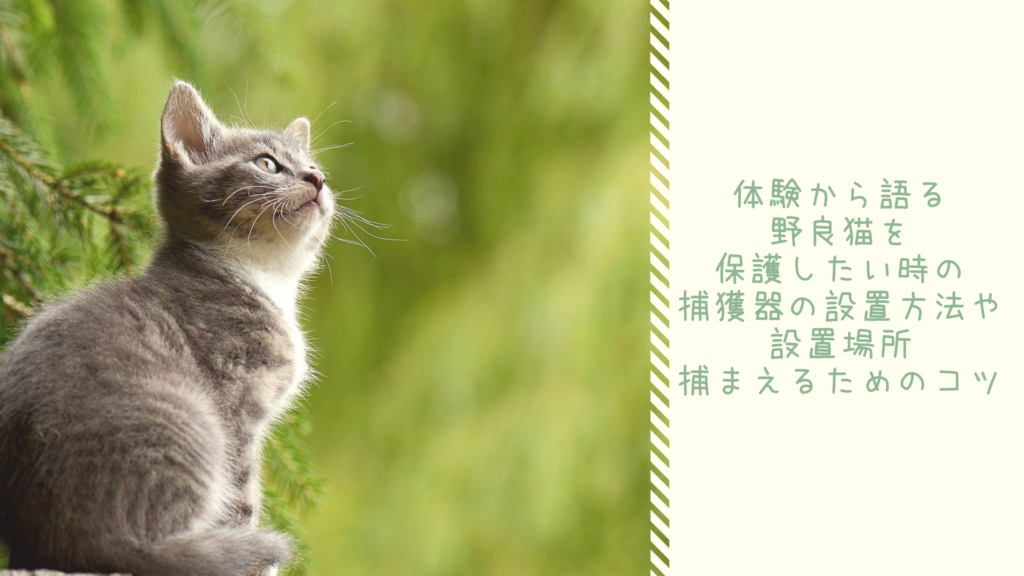最近野良猫の子猫を保護したゆきちです。
その経験から、先日、野良猫を保護するための捕獲器の借り方や貸し出している場所をご紹介しました。
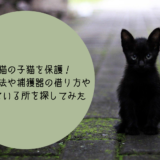 体験談│野良猫の子猫を保護!保護の方法や捕獲器の借り方・貸出している所を探してみた
体験談│野良猫の子猫を保護!保護の方法や捕獲器の借り方・貸出している所を探してみた
今日は、その捕獲器を使って無事に子猫を保護できる方法をご紹介できればなと思います。
具体的には、捕獲器の設置方法とコツ、捕まえた後の対応です。
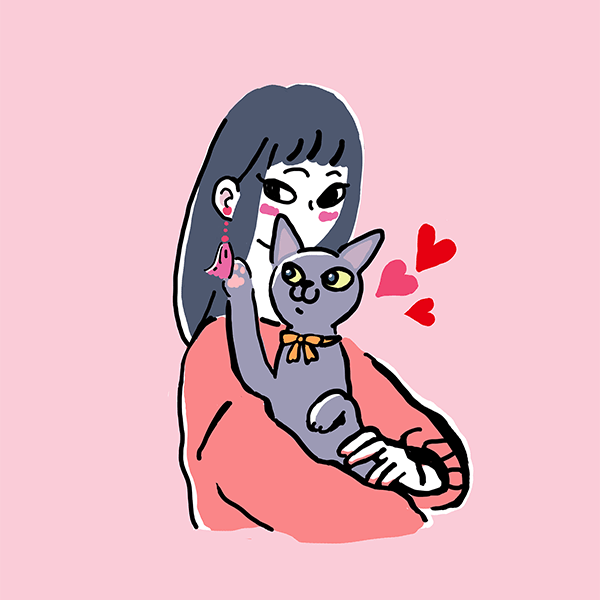
[toc]
野良猫を保護捕獲するために準備するべきもの
では捕獲機の設置方法について説明していきますが、その前に捕獲(保護)する前に必要なものを準備しましょう。
- 捕獲に使用する捕獲器
- 布やタオル(捕獲器にかぶせるので、それくらいの大きさのもの)
- 新聞紙やチラシ(捕獲器の中の床に敷きます)
- エサ(ウェットフード等臭いの強いものが好ましい)
- 軍手、袖の長い服
- 捕獲した後の生活必需品(エサやトイレの砂等)
①捕獲器
捕獲器の借り方や、借りられる場所については、前回の記事をご覧ください。
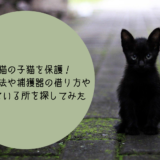 体験談│野良猫の子猫を保護!保護の方法や捕獲器の借り方・貸出している所を探してみた
体験談│野良猫の子猫を保護!保護の方法や捕獲器の借り方・貸出している所を探してみた
②布やタオル
捕獲器にかけるものです。
捕獲器に布やタオルをかけて設置した方が、猫が安心することができます。
猫は暗くて狭い場所が好きなので、つい入りたくなるような
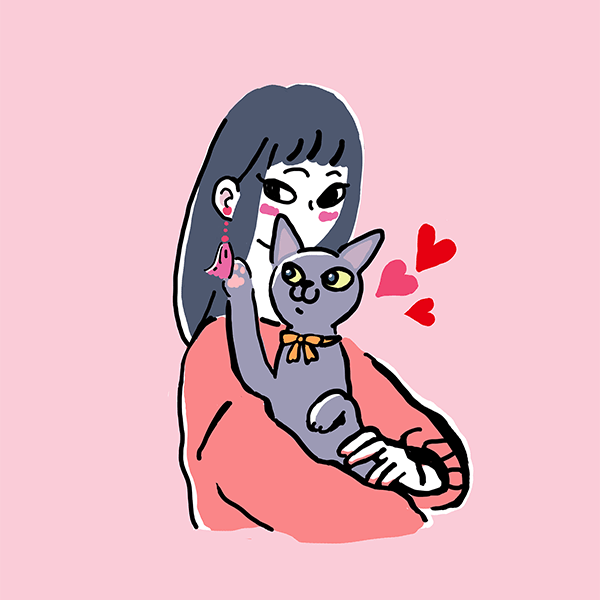
③新聞紙やチラシ
捕獲器の下に敷きます。
エサや猫をおびきよせるものを捕獲器の中に設置しますが、エサがこぼれたときのために敷いておきます。
猫を捕まえて保護することは素晴らしいことですが、他の人の迷惑にはなってしまわないよう、エサをこぼしたり汚したりしないために、忘れないようにしましょう。
また、捕獲器の仕組み(仕掛けを踏むと捕獲器の蓋が閉まる。その踏むスイッチ自体)がわからないように隠す役割も果たします。
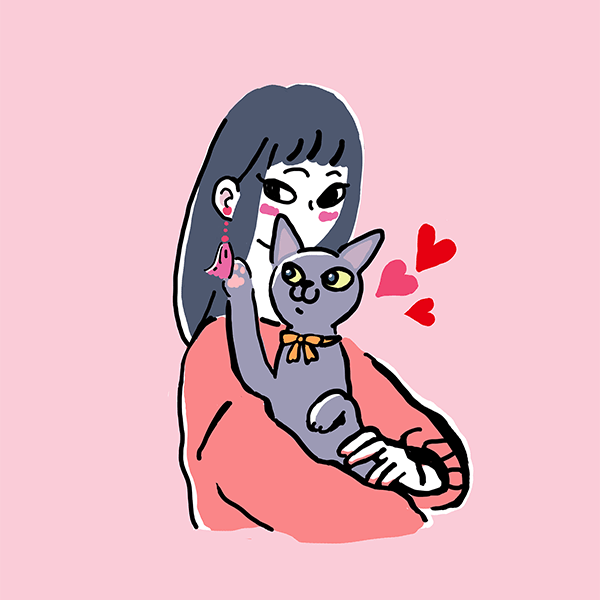
④エサ・食べ物
猫をおびきよせるためのものです。
猫にエサがあることがわかるように、においが強いものを設置するとベターです。
ドライフードなどよりは、水分を含んだウェットタイプのフードがおすすめです。
私はこれを設置しました
エサと言っても、猫に与えてはいけない食べ物もありますので、下手に変なものを置かないようにしましょう。
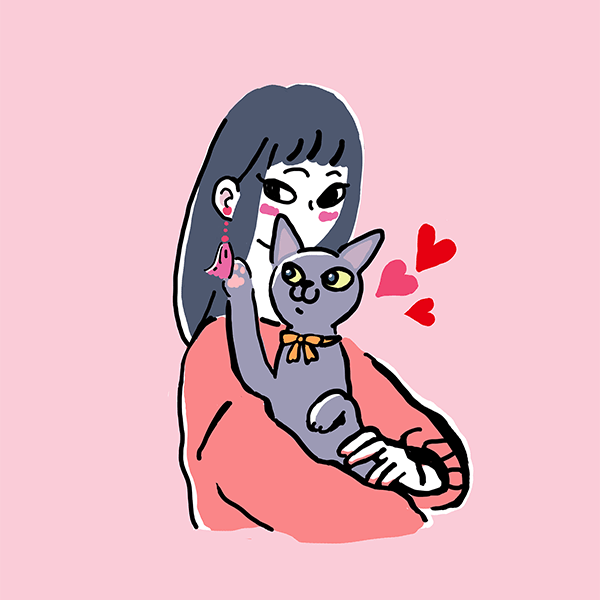
ウェットフードが無難でおすすめです。
⑤軍手、袖の長い服
猫が自然と捕獲器に入ったところを保護しますが、興奮した猫がかごの中から攻撃してくる可能性もあります。
後々、別のキャリーケースへ移す場合も含め、必ず怪我をしないよう、肌の露出を控える服装をしましょう。
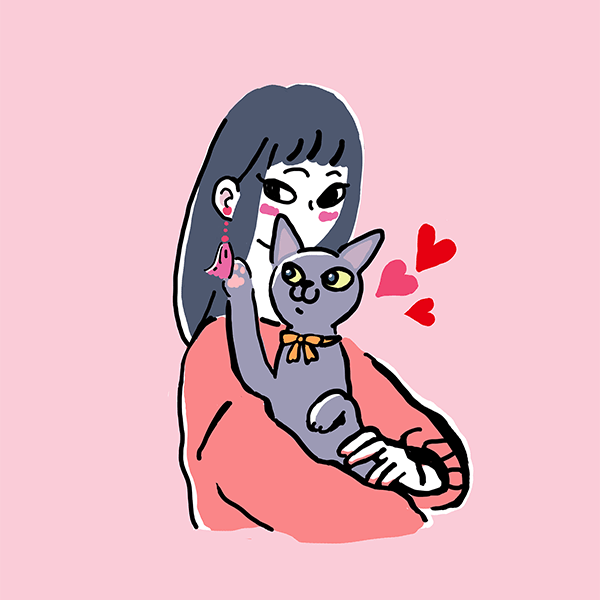
⑥捕獲した後に必要な生活必需品
猫を保護してすぐに誰かに引き渡す、などではない場合、捕獲がゴールではありません。
実際に捕獲したら、そのあとのお世話に必要なものを先立って準備しておく必要があります。
具体的に必要なものや、あった方がよいものはまた別の記事で紹介しますね!
野良猫を保護する!捕獲器の設置までの手順
では、早速捕獲する手順をお話しします。
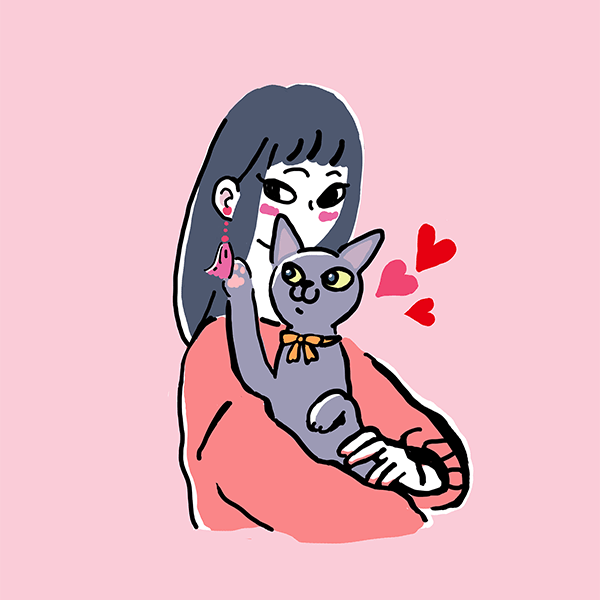
①捕獲器を設置する前に、保護してよい猫か再度確認する
野良猫で可哀想・・・と思いきや、実は外飼いされている猫や地域猫かもしれません。
その場合、勝手に捕獲してしまうと、トラブルにつながりかねません。
地域猫とは・・・
避妊・去勢手術などを行い、繁殖を防いだ上で、地域全体で育てるという活動のもと、面倒を見てもらえている猫のこと。
その活動は、TNR活動(別称:さくらねこ活動)とも呼ばれています。
飼い猫かそうでないかの確実な見分け方法というのは難しいですが、
- 首輪をしているか
- 毛並みが整っているか
- 体つきは立派か(痩せているor太っている)
- 避妊or去勢の手術痕があるか
- 人慣れしているか
- 決まった時間だけ現れる
首輪をしていれば、飼い猫(室内or外飼い)の可能性が高いですね。
もしかしたら迷い猫の可能性もあります。
可能であれば、首輪を確認して、連絡先が書いてあれば、その連絡してあげてください。
電話番号やメールアドレスが書かれた鑑札があり、それを付けている子もいます。
(うちの子がつけているのはこれ↓)
鑑札と首輪が一体化しているものもありますね。
PROSTEEL ねこ用首輪 迷子札 刻印 ブラウン 本革 レザー セーフティー 安全サイズ調整可能 ペットID ネームタグ
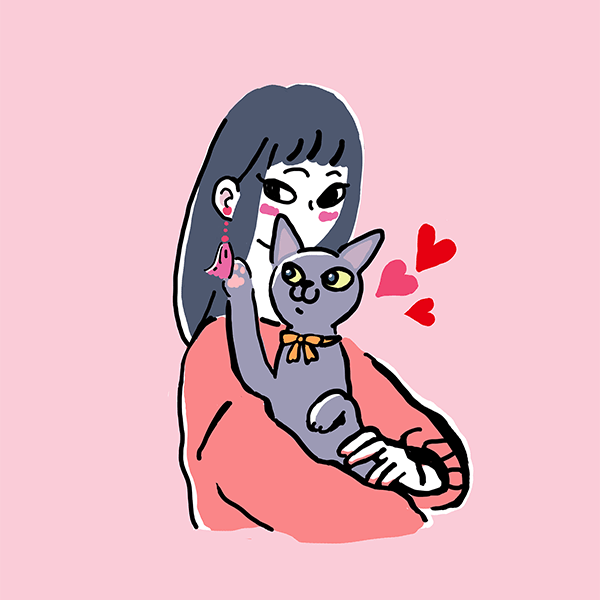
体つきがまるまるしている猫は、外飼いされている猫か、もしくは地域猫である可能性もあります。
また、明らかに人慣れしている場合も、外飼いされている猫や迷い猫の可能性が高いです。
猫が決まった時間に現れる場合も、その周辺でエサをもらっている地域猫や外飼いの猫の可能性が高いでしょう。
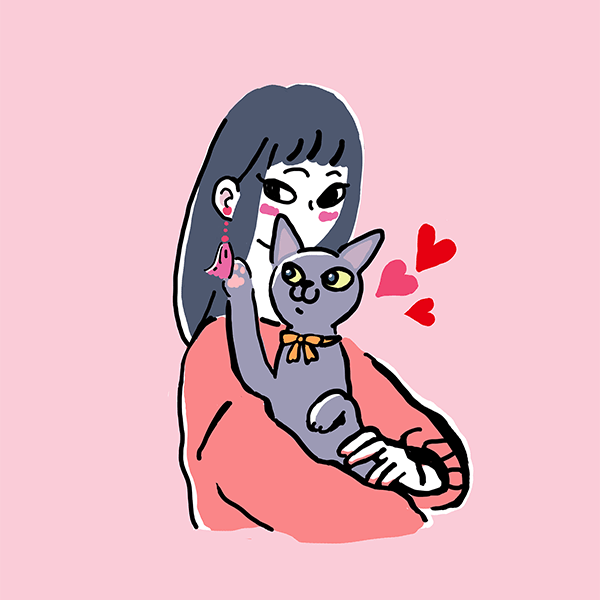
保護した後、念の為誰かの猫ではないか、チラシを近所に配ったり、貼り紙をしたり、SNSで探してみるとよいでしょう。
迷子猫を探している人が投稿しているサイトもあるので、探してみるのもよいでしょう。
明らかな迷い猫は、チラシに加えて、警察に届け出を出してみるのもよいでしょう。
- 明らかに体ががりがりでやせ細っている
- 怪我をしていたり、体調が悪そう(鼻水や目やにがひどい等)
- 虐待を受けている猫
- 親猫のいない子猫
- 衰弱している猫
- とても交通量が多い場所にいる猫や、工事現場近く、取り壊しの決まった家屋の近くに住んでいる猫等
これらは野良猫である可能性が高く、保護が必要な猫かと思われます。
また、注意すべきは子猫の場合です。
まだ幼く、母猫が傍で面倒を見ている子猫のような場合は、保護しない方がよいです。
母親が自分の子猫を取られる(奪われる)と思って凶暴化することもありますし、離乳までは母猫に任せたほうがいいからです。
母猫が来ないか、半日から1日ほどは見守ってみるとよいでしょう。
母や兄弟と過ごしている方が安全であり、彼らにとって良い場合もあります。
ですので、もしもまだ母猫の下で生活しており、特に体に不調などはなく、命の危機がないようであれば、子猫が自分でご飯を食べられるくらい(親離れ・子離れする)に育つまで待つのがいいかもしれませんね。
ただ、明らかに母親がいない(はぐれた・捨てられた)場合や、乳歯が生えているけどうろうろとさまよっている子猫は保護してあげるべきです。
では子猫を見つけ、その命を自分の手で助けたい人は、どうすればいいのか。塩沢さんは、「まず母猫がいないかどうか確認してください。離乳までは母猫に任せたほうがいいからです。そのうえで、母猫のいない乳飲み子、または乳歯が生えていて既に自力でウロウロしている子猫を見つけたら、すぐに保護してあげてください
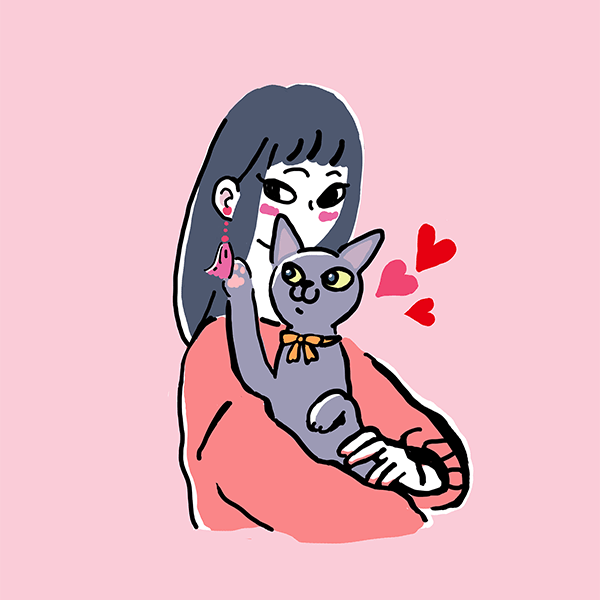
保護した当時の写真↓

目やに、よだれがひどく、鼻周りも傷ついていました。
毛並みもガサガサで、白い毛が黒ずんでいました。
そして、まるで鶏ガラのように骨骨しく、鳴き声も鳴きつかれたのか枯れていました。
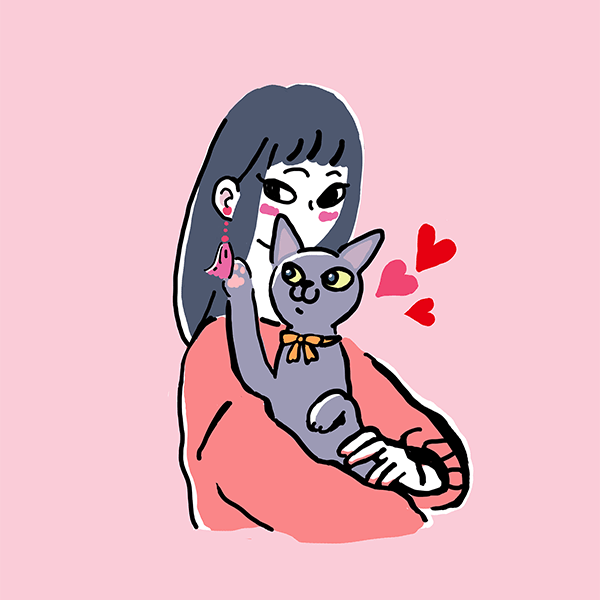
②いざ!保護すると決まったら
捕獲器を設置します。が、可能であれば、近所の方にも野良猫を捕獲するという旨を伝えておく方がよいでしょう。
というのも、捕獲器を設置するとなるとその場所の所有者に許可をもらう必要がありますし、エサを用いて捕獲することによって、何かしらの影響を与える可能性もあるからです。
また、保護する予定の猫が人慣れしていない・警戒心が強い場合、即日での捕獲ではなく、長期戦になることもあります。
(猫がよく出没する場所にエサを置いて、数日間かけてここでご飯を食べられることを知らせてからはじめて捕獲器を設置して捕まえる)
そうなると、迷惑になる確率があがりますので、許可やお伺いを立てたほうがよいでしょう。

ただ、設置場所が住まいの敷地内だったのと、捕獲までに1時間も要しなかったため、大きなトラブルにはなりませんでした
共用部ではなく、私有地であったり、多くの人が利用する場所などに設置する場合や長期戦となる場合は、必ず許可を取った方がよさそうですね。
③捕獲器を設置するのに適した場所
まず、捕獲器を設置するには、それに適した場所、すなわち野良猫を捕まえやすい場所に置く必要があります。
- 人の気配が少ない場所
- 日陰等、過酷な環境ではない(猫の嫌がらない)場所
- 安全な場所(交通の多い場所等にはおかない)
- 安定した場所(崖の上や木の上などではなく、道の上や平らな面の上)
- 猫のよく通る道や、いつもエサを食べている場所
私の場合は、子猫がずっと側溝にいたので、溝にそのまま置きました(笑)
ちょうど捕獲器の横幅と溝の横幅がジャストフィットだったので、猫の通り道でありかつそこを通らずに動くことができないという運のいい状況でした。
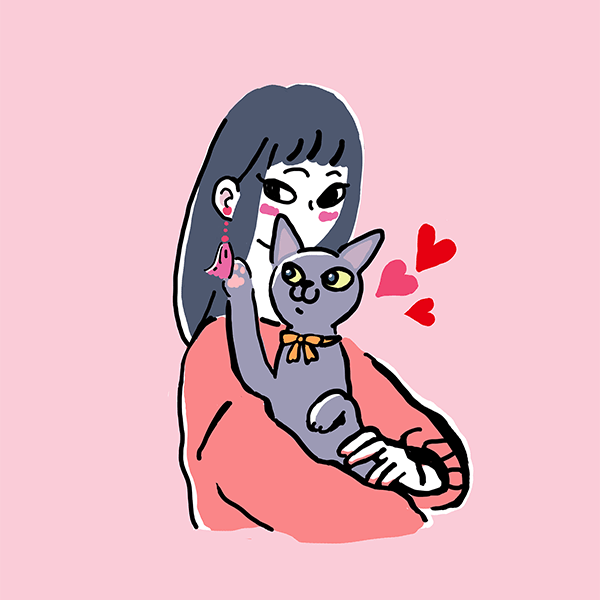
そういった感じではなく、うろうろとうろついている猫でかつ成猫で野良猫歴が長い子だと、きっと一筋縄ではいきません。
猫はざわざわとしたところを嫌う神経質な生き物なので、人通りの少ない場所で上記の条件を満たす場所をあらかじめ見つけ、そこで餌付けをしてから仕掛けるのがよいでしょうね。⇒その場合、エサを与える時刻の少し前にあらかじめセットして待つとよいでしょう。
④エサをセットして捕まるのをじっと待つのみ!
さて、ここまで用意周到にやれば、あともう少しです!
エサのセットをして、じっと待つばかりです。
エサのセットの仕方がポイントです!
- エサは捕獲器の最も奥の方に置く
- 入り口付近にエサを置かない
- においの強いエサを置く
- 安定した場所(崖の上や木の上などではなく、道の上や平らな面の上)
- 猫のよく通る道や、いつもエサを食べている場所
捕獲器の仕組みは、捕獲器の底にあるスイッチみたいな仕掛けを足で踏む(負荷がかかる)と、入り口のドアを開けていたストッパーが外れ、自動的にドアが閉まるようになっています。
ですので、しっかりとそのスイッチ的な部分を踏んでくれないといけないわけですね。
よって、エサを一番奥の方に置かないと意味がありません。
エサを入り口付近から徐々にパラパラとおいて、奥の方へおびき寄せるという手法を使われることもあるようですが、その入り口のエサだけを食い逃げされないように(猫は警戒心が非常に強いため)その奥まで来ないとエサまでありつけない状態にあえてすることで、捕獲する確率を上げるのです。
では、どうやって一発で奥まで来てもらえるようにするか?
それは先ほどもお話ししましたが、においのつよいエサを置いておびき寄せるのです。
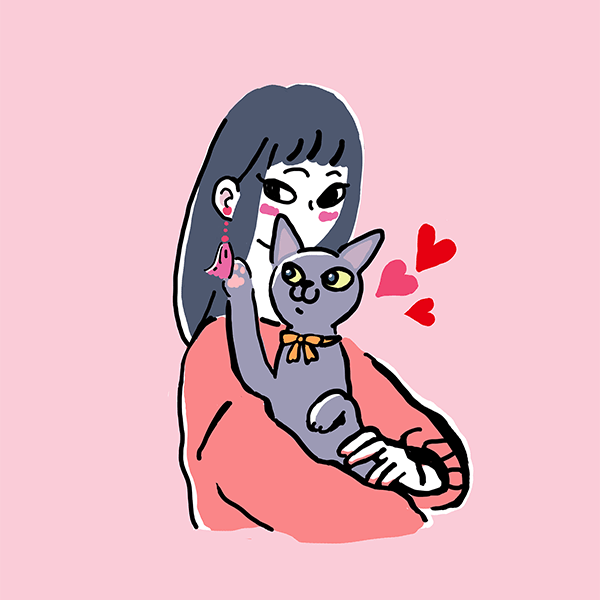
ちょっと健康的に大丈夫なのかな・・・と思いますが、あくまでも捕まえるための少量でかつ1回きりなので大丈夫ということでしょうか。
餌は猫缶やドライフードも使えますが、鶏のから揚げ(骨なし)は経験的に成功率が高いです。
引用 湘南鎌倉猫ほっとさぽーと
また、エサを入れる器は、プラスチックのお皿や、紙皿などの壊れないものにしておきましょう。
猫が捕まった瞬間驚いて暴れる可能性もありますし、壊れると危ないからです。
また、警戒心が強くつかまりにくい猫の場合は、(踏み板をなかなか踏まない猫)捕獲器の奥の方で、上からエサをぶらんと吊るすと効果があるようです。
捕獲器の網の部分に紐で縛ってぶら下げるイメージでしょうか。
捕まりにくい猫(踏み板を踏んでくれない)には、上から餌をを吊るすと効果がある場合があります。この場合もケージのできるだけ奥の位置に縛ってください。
アリが多い場合も餌を吊るとアリがたかりにくいです。引用 湘南鎌倉猫ほっとさぽーと
私はエサと一緒にミルクまで用意しちゃいましたが、捕まえるという名目だけであれば、エサだけで事足りるでしょうね。
私はのどを潤してやりたいという思いから入れちゃいましたが、こぼれてしまうのを防ぐためにも、エサだけの方が無難かもしれませんね。
⑤捕獲器をしっかり監視しよう
捕獲器を設置したら、可能であれば遠くからずっと見張って置き、捕まった瞬間そのまますぐ引き上げるのが理想です。
放置しすぎると、暑さ寒さ等の劣悪な環境などから猫のためにもよくないですし、近所の方の迷惑になりうるからです。
野良猫歴が長い猫や長期戦を強いられている猫の場合は、ずっと見張るのが難しいと思うので、そういう場合は定期的に捕獲器をチェックしましょう。
捕まっていることが分かればすぐにそのまま引き上げましょう。
捕獲までに長期間かかりそうな場合は、所有地の方の許可を得てから、事前に捕獲器を設置しますよ、という旨を書いた貼り紙をしておくとよいでしょう。 +自分の連絡先などを記して知らせておくとなおよいかもしれません
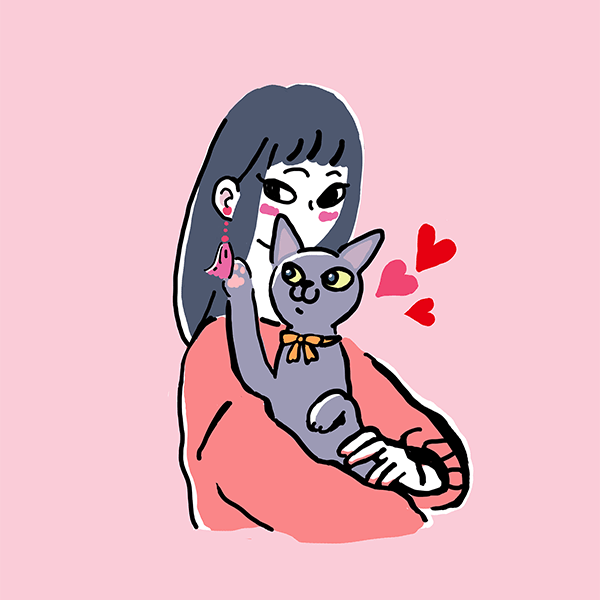
1時間ほどすると、今までの鳴き方と少し異なった鳴き方に変わったので見に行くと、バッチリ捕まっていました。
布はかぶせたまま、捕獲器のふたなども開けず、軍手をした状態で取っ手部分をもって運びましょう。
他にも、
- 入れておいたエサが腐っていないか
- 保護したかったはずの猫以外の猫が入っていないか
- 捕獲器に不具合がないか(壊れていないか)
なども定期的に確認するようにしましょう。
どうやって猫を捕獲するの?捕獲器の仕組み
実際の捕獲器のしくみについて、実際の写真を交えてご紹介いたします。
(Coming Soon 写真準備中です。近日公開予定)
猫を保護した後はどうすればよい?
①動物病院に連れていく
無事に猫を捕獲できたら、そのまま動物病院に連れていくのが理想です。
野良猫は、色々な病気や感染病に感染していたり、ノミダニ、その他寄生虫などが寄生している可能性などがあるからです。
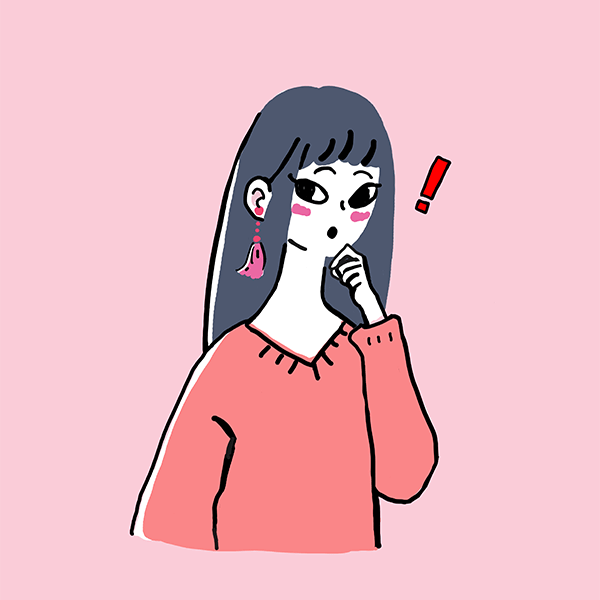
キャリーケースに移してから連れていくとよいという意見もありますが、攻撃される可能性もありますし、キャリーケースを持っていない場合もあると思うので、そのまま病院に連れて行ってもよいと思います。
入れ替える際に逃げられてしまう可能性もありますしね。
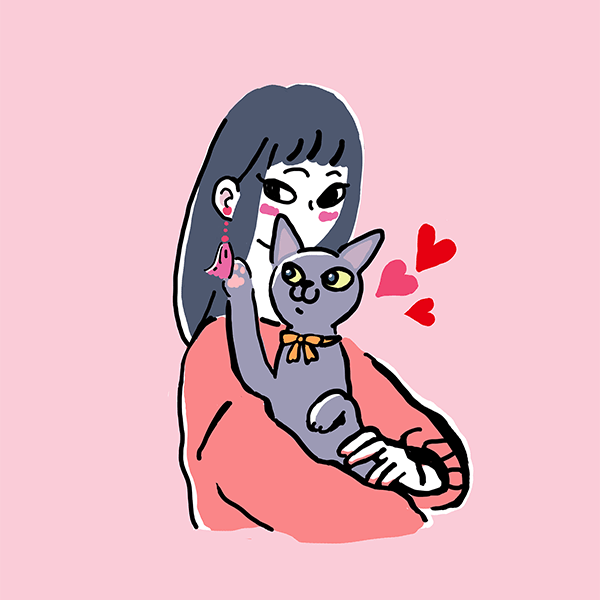
それでも特に不具合はありませんでした。
トイレも小さな器に入れておいてあげて、食事とミルクも入れましたし、布をかぶせた状態だったのでその方が安心して居心地もよいようでした。(人間の姿を見たり、先住猫を見たときに威嚇していたので)
病院にも、野良猫を保護したといえば、特に問題なく、理解して頂けました。
キャリーケースにどうしても移したい場合は、捕まえてすぐではなく、少し時間をおいてから(暴れる可能性があるため)
また、軍手をして肌の露出をなくしてから、先住猫と共用のキャリーケースは極力避けること、
これらを満たしていればよいかなと思います。
動物病院で見てもらうこと、やってもらう処置(やっておいた方がよい処置)や、その費用などに関しては、別の記事でご紹介しようと思います!
②迷い猫か保健所やSNSで確認する
先ほども捕まえる前に確認する事項でもお話ししましたが、もし飼い猫か判別がつかないけれど、衰弱している場合や、危険が迫っている場合は、一旦捕獲してからでも、保健所や警察署に問い合わせて、迷い猫や飼い猫ではないかを確認しましょう。
こちらからも警察や保健所に「こんな猫をいつ保護しました」と届け出ておくと安心でしょうね。
迷い猫とわかったときは、警察に届け出をだしてから、迎えが来るまで預かり飼育となります。
最近はSNSが発達しており、そこで迷い猫の情報が拡散されることが多くなっています。
「捕獲した地域名+迷い猫」などと検索してみることをおススメします。
また、地域猫の場合もあるかもしれないので、その周辺で活動しているボランティア団体などがあれば、一度問い合わせてみるのもいいですね。
③実際に世話をする もしくは里親を探す
迷い猫や飼い猫・地域猫でもないとわかったら、実際に飼育していきましょう。
飼育するために最低限必要なものに関しては、こちらをご覧ください↓
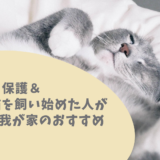 野良猫を保護&初めて猫を飼い始めた人が買うべき我が家のおすすめ必要なものまとめ
野良猫を保護&初めて猫を飼い始めた人が買うべき我が家のおすすめ必要なものまとめ
里親の探し方も、また別の記事でご紹介します!(Coming Soon)
保護する前に今一度ご確認を!
保護しよう、という心意気は立派で、是非1つでも多くの命を救ってほしいと思います。
ただ、捕まえたものの今後のめどが立たない・・・という状態は避けてほしいです。
里親を探すか、自分で飼うという準備が整えられることが定まってから保護しましょう。
- 先住猫との相性が悪い場合の対策が考えられている
- 初めて猫を飼う場合、同居する家族にアレルギーの人はいない
- 外飼い厳禁・家の中で飼うことができる
- ペット飼育OKの物件に住んでいる
- 猫を飼育する財力があるか(毎年予防接種、避妊・去勢手術料、病気に伴う通院費等)
- どんなことがあっても絶対に手放さずに飼えると誓える
上記項目をしっかり満たしたことを再確認してから、保護してあげてください!
まとめ
超大作になりましたが、猫を保護・捕獲する上で必要なことや大切なこと、捕獲器の設置方法などについてご紹介してみました。
無事、野良猫を保護できた後にまずすべきことはこちらでまとめていますので、このままご覧ください★
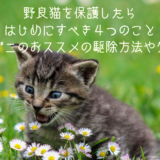 野良猫を保護したら初めにすべき4つのこと│ノミダニのおススメの駆除方法・シャンプーや子猫の方法も
野良猫を保護したら初めにすべき4つのこと│ノミダニのおススメの駆除方法・シャンプーや子猫の方法も
捕獲しようとしている方の参考になれば幸いです^^
あわせて読みたい!
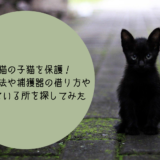 体験談│野良猫の子猫を保護!保護の方法や捕獲器の借り方・貸出している所を探してみた
体験談│野良猫の子猫を保護!保護の方法や捕獲器の借り方・貸出している所を探してみた